
私が講師についてピアノのレッスンと作曲の勉強を始めたのは大学に入って間もなくのことです。
このことについては他の記事の中でもお伝えしています。
ですがその後しばらくして後、ある曲のイメージが徐々にできあがり、それが延々と今に至るまで何度となく手直しを経て作った曲、というのがあります。
それが実は今回ご紹介する自作曲『フルートとピアノの小品 変ホ長調「春風」』です。
決して大層な曲などではありませんが、そういうわけで自分にとってけっこう思い入れもあります。
今回はこの「春風」について、その作曲のいきさつとともにご紹介していきます。
音楽の勉強スタート頃から隣り合わせの「春風」ー今でも直すことが
そういうわけで、まずこの自作曲フルートとピアノの小品 変ホ長調「春風」
をご紹介しますが、上にもお伝えしたように、この曲は、いわば私自身にとって音楽の本格的な勉強の長い経過と隣り合わせで存在していたようなところがあります。
ピアノを習い縦の一番早いうちに、曲冒頭の断片が浮かび上がり、後になってそこに続く部分を作り上げていきましたが、今でもこの『春風』は、ちょいちょい直したりしている、そういう曲になります。
形式的には3部構成で、いわゆる「サンドイッチ」タイプになります。
つまり三つの部分の内、最初と最後が大体同じ要素で構成され、真ん中がそれに対して対比的な部分、ということです。
曲のイメージは「癒やし」?自分でウォークマンで聞いて楽しむことも
作曲テクニック的にはそれほど難しい構成もなく、自分で言うのもナンですが、以前運営していた自己サイト『hiromichiの部屋』などでも、リンクを張っていただいている方たちを中心にけっこう人気があったといえるかも知れません。
実際、知人の方たちにこの曲を聴いてもらうと「癒やされる」という評価が多かったようです。
確かに曲想的にも、そういう「くつろいで聞ける」「慰めになる」曲なのでは、と思います。
実際、この曲はおよそ30年前くらいから構想が生じ、その後いろいろと細かな改変を重ねながら今日に至ります。
いつもこの曲、自分でウォークマンに入れて自分で聞いていますが、ちょっと前までは別な自己サイト「丘の上の小径(こみち)」(現在廃止)にもアップしていました。
今回、今のところの最新版になりますが、今後自分の好みによってはまたちょこちょこ直していくかも知れません。
というわけで、よろしければご視聴ください。
(注:他の自作曲もそうですが、著作権は放棄しておりません。ー申し訳ありませんが念のため)

「春風」の変遷ー初期の頃から大分変わったところも
春風が長い年月間でどう変わっていったのか、その経緯をちょっとお伝えしましょう。
この「春風」、上でもお伝えしたように、時折思い出したように何度も直しを入れていたりするため、初期にできあがった頃とはずいぶん変わったりした部分もあります。
やっと作り上げて、それを録音して聞き慣れてくると、なんかまだ不満なところが出てくる、そしてしばらくして修正のアイデアが頭に浮かんで、それでまた直す、そんな堂々巡りのような経緯があるのがこの「春風」です。
そしてそれは、譜面上のことだけでなく、作曲ソフトの変更に伴って、音源の変化にもまた現れています。
最初の頃はRolandの作曲支援ソフト総合パック(?)『ミュージ郎』に同梱されていたMIDI音源作曲ソフト『Musicator』で作っていましたが、数年後にはそれが同じRolandの『Cakewalk』に移り、その後さらに河合楽器の『スコアメーカー』に変わって今に至ります。
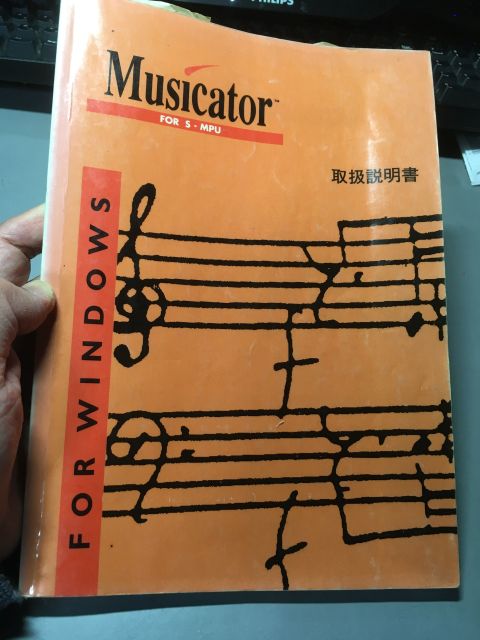
最初にこの曲をサイト上にアップしたのは、やはりかなり前、今からおよそ20年は経ちます。
何しろWindowsのバージョンが3.1の頃に初めて作曲がスタートし、98くらいでサイト(ホームページ)を開設し、そこで初めてこの曲がアップされているはずです。
このブログでは、前身となった自己サイトとしてホームページ『丘の上の小径』をご紹介していますが、『丘の上の小径』を運営する前は、『hiromichiの部屋』というホームページを運営し、その中で初めてこの曲もご紹介しています。
こちらのブログ上の音源はMP3ですが、その『hiromichiの部屋』でこの曲をご紹介していた頃はまだMIDI音源で、一回り二回り音質も乏しいものでした。
そして併せて、自己評価の範囲ですが曲の内容もこちらのブログのそれよりももっと劣っています。
逆に言いますと、この「春風」はそれ以来、改訂を重ねて次第に形を整え、ようやく今の形になっていると言うことになります。
一方、その一番初期の『hiromichiの部屋』でこの曲をご紹介していた文章がまだ手元に残っています。
自分的にはけっこう懐かしく、さらにそれ以前にこの曲のアイデアが浮かぶことになった東京の練馬区に住んでいた頃、その隣の新座市で散策した写真画像もあったので、その画像を文章とともにアップしてみます。
写真とは言っても往年の銀塩フィルムを使ったコンパクトカメラの画像のため、元々が不鮮明になっていて、しかも今はご覧の通りセピア色に変色したりしています。
なんとも時代を感じさせるような遺物みたいになってしまっていますので、そこはご容赦ください♫
以前に「春の小川」をテーマにした曲をアップしましたが、私にとって春は好きな季節です。でもその一方で花粉症の自分にはつらい時期でもありますね。
だから必ずしも手放しで好きになれる季節でもないですが、それでもやっぱり四季のうちでは好きな方だと思います。
この曲は原型として初めて形になったのがだいたい20代の前半です。冒頭のⅠーⅥーⅣ7(Ⅱ1)ーⅤのコード進行とメロディを手持ちのシンセサイザーキーボードでよくポンポン弾いていました(これしか弾けませんでした(泣)。)。
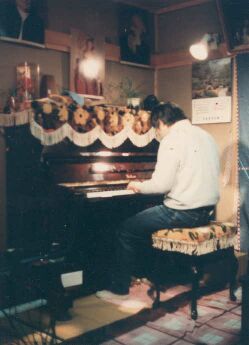
確か二十歳そこそこの頃です。
なお、グールドのまねではありません爆
その当時私は東京の練馬区に住んでいましたが、近辺の武蔵野の野原が好きでよくトレッキングしていました。
近い所では大泉学園の先の市場坂橋を渡って、埼玉県の新座市や朝霞市、ちょっと距離を伸ばすと上福岡や鶴瀬、あるいは与野市まで、日中一杯かけて歩き回ったものでした。

20代の若者にしてはずいぶん妙な娯楽のように思われるかも知れませんが、なぜそんなことをしたかというと、武蔵野特有の淡い緑の田園風景にたまらなく惹きつけられたんですね。
私が田舎育ちのせいも関係していると思いますが、東京郊外の武蔵野の、家並みが途切れて野原になるところまで歩いて行き、草の香りや雑木林の木立が風に吹かれて葉ずれの音を立てるのを聞きつつ、時には小高い山や林の中に分け入って道を選ばず散策する、それが20代前半の自分にとっては東京住まいの息抜きのひとときでした。
特に好きだったのは練馬の大泉学園を通って新座市の田園地帯を抜けて柳瀬川を過ぎ、東上線の上福岡までテクテク歩いていく、というパターンです。
広々とした野原や田畑、雑木林を分け入るのは本当に気持ちよかったですね。都合3~4時間くらいかかったでしょうか。今でも思い出すと行ってみたいと思いますけど。(でも関越自動車道の高架にさしかかった時だけは車の音がうるさかったな~(^^;)。それに結構足にマメ作って帰宅しましたね(笑)。)

この曲は言ってみると、そんな武蔵野へのあこがれを曲の断片に直し、それをまとめて作り上げてみたものです。
なお、最初はフルートの音をメロディに持たせてみましたが、音がどうしてもヴィブラートにすることができず、どうしても不自然な音だったので、ストリングス(※)の音色に変えてみています。
※
上の文中で「ストリングス」とありますが、当時『hiromichiの部屋』でアップしていた「春風」はストリングの音色にしていました。
今こちらのブログではお聞きの通り、それほど違和感がないのでフルートに直しています。
こんなところからも、時間の経過というのは自分自身にとっても胸に響きますね。
終わりに「こぼれ話」ーそのうち実際に演奏してもらえるかも
というわけで、この「春風」は自分が音楽を本格的に勉強を続けていた、そのスタート時点からいつも陰に寄り添っていたようなことから、ある意味自分にとってのライフワークのようになっている曲、といえるのかも知れません。
そして私の初期の頃にできあがった曲想や内容がけっこうシンプルなので、それほど実際の演奏では困難なものではないと思います。
ですのでごく最近、20代に東京にいた頃、音楽を習っていた先生や自宅の近場にある音楽の先生に頼んで演奏してもらうように頼んだ経緯があります。
いまだ返答も受け取っていないので、どうなるかは不明ですが、もしかしたらいつか、小さな発表の場などで実際に演奏してもらうことができるのかも知れません。






