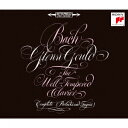『平均率』という言葉で連想するのはやっぱり『バッハ』ではないでしょうか。
本来的には「1オクターブを12『等分』した音と、その集合体」のようなことを指すと思います
(より正確な定義はこちらのWikipediaなどで参照 → https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5%BE%8B)
が、ほとんどの人はバッハの『平均率クラヴィーア曲集』という一連のキーボードの曲集を考えてしまうのではないでしょうか。
そして、彼がこの曲集を生涯で二組作ったことは、音楽に詳しい方なら誰でもご存じだと思います。
これら2つの曲集のうち、私(hiromichi)はどっちが好きで、それはどんな理由からか、と言うのが今回のテーマとなります。
グールドの演奏はハイレベルすぎだった?あの「風変わりな演奏」に判断が行ったり来たり
あくまでも私はアマチュアであり、音楽に対する造詣もその域を出ることはありませんので、単に自分の好みで判断しているに過ぎないコメントの連続であることを付け加えておきたいと思います。
平均率という曲集に初めて触れたのは高校時代でした。グレングールドのレコードで第1巻を聞いたのが最初です。
その後大学入学時の前後にリヒテルの演奏によるテープで第2巻を初めて聞きました。つまり1巻を初めて聴いたのがグールドの演奏、2巻を初めて聴いたのがリヒテルの演奏だったというわけです。
この両方のピアノの巨匠は、演奏の奥深いところについては賢知もできませんが、少なくとも表面的な演奏内容について言えば、“両者は全く対極のポジションにある”。そういうとらえ方を私自身しています。
あくまでも私個人の独断偏見、そして浅い知見での判断ですが、こう言えるんじゃないかと思います。

グールドは結構『特徴的なスタイルで前衛的、先鋭的なピアニストという印象』と言うような内容の文献を読んだ記憶を持っていました。
確かにレコードを聴いていると、ずいぶん“変わった演奏だな?”みたいな印象を持った記憶があります。
グールドの演奏になじみのある方ならご存じのとおり、いろいろと“風変わりな”演奏です。
ただ、高校時代には他の演奏者では平均律を聞いたことがないも同然で、比較のしようもありませんでした。
「こういう曲なのかな」
みたいに納得していましたし、レコード店(当時はレコードが音楽メディアの主流だったので、こういう種類の店になります)に行くとグールドのレコードは目立っていたので、他に「イギリス組曲」「インヴェンションとシンフォニア」も買って聞いたりしていました。
著名だし優れた演奏家だとは思いましたが、先鋭すぎているのかどうかの判断に迷う、それ以前に単純な私の耳にはどことなく上滑りのような感じに聞こえる一方で、「こういう曲なんだろうな」という納得の仕方を自分に強いていた自分がいる。
聞いていて戸惑いながらもう印象があったりします。
ですがそれとは対照的にリヒテルはすごく正攻法的な印象を持ちます。
言ってみれば
「これぞ本当に上手なピアニストの弾き方」。
子供のような表現でお恥ずかしいですが、そんなとらえ方で自分的には考えています。
グールドに比べてどう言うべきか、“譜面通りに、そして普通の人の求めるとおりに弾いてくれる”みたいな感じでしょうか。
だから、自分にとってはリヒテルの演奏の方がなじめる印象です。
(自分の独断で総評した所見です。これだけでも充分偏りがあると思いますがどうかご容赦を)
ただ、グールドの『平均律2巻』はそれでも好きで、1巻よりもよく聴いていた記憶があります。実際大学生活で東京に移り住んでいた頃は、リヒテルの2巻のカセットテープが劣化して聞きづらくなってきてしまったこともあり、グールドの2巻の演奏の方をよく聴くようになっていました。
そういう両者の演奏の違いもあるかと思いますが、結論から言ってしまうと私は今日に至るまでほとんどもっぱら第2巻を愛聴していました。
不思議なのは、グールドの演奏のうち「平均律1巻」はどうしても耳が馴染みきれず、一度二度レコードを買ってきいた後は投げ出し状態だったものの、大学時代に図書館で借りた「2巻」はかなりよく聴き直しています。
グールドの演奏は多くの方がご存じの通り、グールド自身が自分の思考や音楽表現に合わせて各曲の演奏やタッチをずいぶんと変えたり、場合によってはテンポまで自由に操ったりしてしまう傾向がありますし、実際「1巻」の第1曲「前奏曲」などは高校時代、初めて聴いて面食らった記憶があります。
それに対して彼の「2巻」は、そういう自由さが「1巻」のときと比較してずいぶん控えめなのか、オーソドックスに回帰しているのか、はたまた私自身の聴き込みが足りないのか勘違いなのか知りませんが、けっこう安心して聴ける内容になっていた印象があります。
専門家の間でどういった解釈見解があるのか?この彼の「2巻」についてはそこまでの興味もわかずに謎のまま今に至りますが、少なくともリヒテル同様、あるいはそれ以上に「好きになれた『2巻』」、今はそういう結論になっています。
聴いていて「耳に優しい」「ゆったり感満喫」は2巻?
ところで私が第2巻を好むのは『なぜ?』と言われたら、やっぱり聞いていて楽しいから、と答えるしかないです。
実際、私の中で1巻と2巻とでは嗜好とともに聞く頻度がかなりの差異を持っています。
なぜそんな風に差異を持つかというと、やはりこの2つの曲集の間にはある一定の違いがあるからだ、と言えそうです。一つには2つの曲集の音楽的な内容の作曲者のバッハが1巻を完成したのは確か1722年、2巻は1744年と記憶していますが、この20年あまりで彼の作風や書法がさらなる熟達を遂げたと思います。
私は専門家ではないので安易に断定も評価もできませんが、細かなところで例示を持ち出すと、2つの曲集のうち、それぞれ第一曲の「前奏曲(ハ長調)」を比較すればよいかも知れません。
2巻の方が聴き応えあり?
次にそれをちょっとご紹介しますと、第1巻はご存じの通り、「グノーのアヴェマリア」で知られるものですが、始めから終わりまでほとんど一定の音形を連続しているのに対し、第2巻は和声や音形、調など音楽を構成する要素が絶えず複雑に変化して流れ、堂々とした4声体の対位法音楽です。
この前奏曲は元々彼が若い頃作曲したものを膨らまして再構成したと言う下りをもつことをある書籍から知りましたが、この2巻を完成した時点の彼の書法は私のようなアマチュアが見ても明らかに若い頃のレベルを凌駕しているようですね。
もちろん2巻にもこのような同じ音形を連ねて和音の変遷のみを追求するものもありますが(嬰ハ長調の前奏曲など)、そこに与えられた音形はもちろん、曲想や響きもかなり複雑化していると思います。
それからもう一つは一つ一つの音楽の長さがありますね。
もちろん2巻の方が1巻よりも個々の曲が長くなり、ある一定のユッタリ感があると思います。1巻はどちらかというと求道者的な感じを受け、音符の構成は2巻ほど複雑ではないものの逆に1音1音が恐ろしく先鋭で、音の意味合いが深く切り込んだ印象を受けます。
また、曲も1巻、2巻の間でそれぞれ番号が対応する曲同士を見てみると、2巻よりも短いものがほとんどです。
1巻の印象としては確かに美しい印象はあるのですが音楽がすぐ終わってしまい、ちょっとものたらなさを受けるというのが私の感想です。
対して2巻は何というか、結構遊び心が出てきているような感じを書法の上から持ちます。
ごくごく平たく言えば、「聞き流すように聴ける」「ゆったりした思いで聴いていられる」「楽しんで聴ける、聴いて楽しめる」のが2巻の強みでしょうか。
一言でこれらを言い表すと、「2巻は1巻より聞き応えがある」と言えるでしょうか。
くどいですがあくまでも私個人の独断偏見です。
リズムの多様さ、変幻自在さも1巻を凌ぐと思いますし、曲を聴き続ける際はこちらも「聞く準備(?)」を持て、前の曲からの曲想や音楽の移り変わりを楽しみながら味わえる余裕が持てる感じがします。

彼がもしももう少し長生きで、たとえば「平均率第三巻」を完成させたらどのようなものになったか?
興味深い疑問ですね。
1巻から2巻への変遷によってある方向性が示されているとも考えられるのでは、と思います。ですのでその延長上のものを想像できると思いますが、それこそ前奏曲の後のフーガには、1巻2巻にはなかったような、もっと壮絶な作曲技巧を含ませた曲、たとえば四重フーガなどを入れたかも知れませんね。
彼は65歳で生涯を閉じましたが、そんなことを考えると、70歳80歳くらいまで生きていて欲しかったです。スピ的に話を広げると、あの世で今も頑張って作り続けているかも知れません。WWW
そんなわけで以上は全て私の独断でした。失礼いたします。
(自前ブログ『丘の上の小径』より転用・修正、2025/05/10再構成)